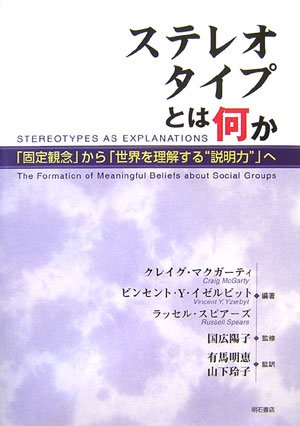傑作短編『ルックバック』。
長編マンガ『チェンソーマン』で知られる漫画家・藤本タツキの新作短編『ルックバック』が好評だ。わずかひと晩で閲覧100万回を超え、いまなお読まれている。ぼくも読んだが、優れた作品だと感じた。発表形式の新しさも含め、話題になることはよくわかる。

ところが、いま、この作品に対し思わぬところから批判が加えられている。作中の殺人者の描写が「統合失調症患者への差別」だというのだ。どういうことだろうか。具体的には、ここでまとめられているツイートが発端になっている。

以下、該当ツイートを引用しよう。
とりあえず、これが『ルックバック』批判派の主な主張である。
カオスのかまど。
このツイートが呟かれたあと、議論は百出し、現在は混沌のかまどで炎がぼうぼうと燃えている状況にある。さて、ぼくたちはこの主張をどう受け止めるべきだろうか? 『ルックバック』はほんとうに差別的な作品なのか? それとも、この主張には誤りがあるのか?
今回、名指しで批判された杉田俊介氏はあっさりと自分の問題を認め、「偏見の助長に無防備に荷担した」ことを謝り、「統合失調症の犯人の描写はやはりアウトだと思う」と語っている。このような態度をどう考えるべきなのか。
以下、その点について考えていきたい。そのまえにひとつわりとどうでもいい前提を書いておくと、ぼくじしんが統合失調症当事者である。
少なくともそう専門医の診断が下っているうえ、障碍者手帳も所有している。現状、20年以上にわたって投薬を続けていることもあって幻聴などの症状は出ていないが、まず問題なく「統合失調症の当事者」であると名乗って良いだろう(そもそも統合失調症を名乗るために一々資格が必要なのかという話もあるわけだが)。
以下の内容はすべてその統合失調症当事者の立場から書く。そういうことだと思って読んでいってほしい。
批判意見その一。
まずは、ぼくと同じ当事者の立場として、作品に批判を加えた意見をいくつか見ていってみよう。たとえばこのような意見がある。
仮定の話ではあるが、この「ルックバック」は、京アニへの放火犯とその事件を題材にしているのかもしれない。私が「ルックバック」において気になったのは、“名もなき放火犯“、あるいは斧を持った男への描写だ。彼はひどい被害妄想に囚われており、事件を起こす。特徴的なのは、視点人物の友人がいる部屋に、斧を持った男が侵入する場面だ。
彼は遭遇した視点人物の友人に、意味不明なことを捲し立てる。
ここで私は「ああ、彼は“統合失調症”と揶揄された青葉容疑者へのオマージュなんだな」と考えた。
もちろん青葉容疑者を擁護する気は全くないし、むしろ厳しい罰を受け入れるべきだとも思っている。問題は、芸術の力によって「統合失調症」に罹患する人のイメージを、怪物のように仕立て上げてしまったということだ。
(中略)
もし自分の属する集団が「犯罪者予備軍」としてみられ、恐怖の対象となっていたら、どう思うだろうか?
京アニ放火事件が起きた当時、ネット上には統合失調症へのヘイトスピーチで溢れていた。なかには統合失調症を罹患する者の断種を推奨する書き込みも多数あり、T4作戦が行われたナチスの時代と何ら変わりないという事実を、私は突きつけられてしまった。
藤本タツキ先生の「ルックバック」はとても素晴らしい作品であったけれども、大衆が抱える統合失調症への嫌悪感を投げつけられたようで、少し寂しかった。こういうことを書くあたり、私は“苦痛を耐え続ける美しい障害者“にはなれないと思う。
でも、それでいいか、とも思う。
批判意見その二。
それは作品中に描かれている通り魔殺人の犯人のことである。漫画の中でははっきりと「統合失調症」と書いていないが、「絵画から自分を罵倒する声が聞こえた」という新聞の見出しが描かれていて、聞こえない声が聞こえるのは「幻聴」であり「統合失調症」の症状である。
精神疾患の患者が映画や小説、漫画などに登場する時がどんな時かというと「常人には理解できない殺人犯。異常者」という役回りがほとんどである。弱いものを助けたり、ヒーローになる精神疾患の患者は出てこない。
もちろん、現実に精神疾患の患者が凶悪犯罪を起こしているという意見もあると思うが、きちんとデータが取られており、精神疾患の患者と正常な人が起こす犯罪の数は、正常な人の方が多いのである。
(中略)
最近、ネットフィリックスで「風と共に去りぬ」の配信が中止になった。差別的な表現が現代にそぐわないのが理由である。
私は今回の問題はこの事件と似ている気がしている。今の時代ではジャンプに掲載され、単行本も出され、賞賛する人が多いけれど、時間が経ち、社会の認識が変わったら、「ルックバック」自体、社会から抹消されるのではないだろうか。
擁護意見。
これらの批判意見を見ていて気付くのは、少々表現が回りくどく微妙であることである。それはおそらく上記引用のなかでも触れられている通り、この作品のなかにはっきりと「犯人が統合失調症である」と描写した箇所は存在しないからだろう。
この作品を読む限り、犯人はたしかに幻聴を耳にしているように見えるが、その原因はさだかではない。べつの理由で幻聴が聴こえていると捉えることもできるだろう。当然、そのことを指摘する意見もある。
藤本タツキの『ルックバック』、通り魔殺人犯の描写について、
「統合失調症を想起させる」「統合失調症を社会悪のように描くな」といった批判が寄せられている。
私自身は上記の批判がピンと来なかったので改めて読み直してみたところ、
作中で“被害妄想により自分を罵倒する声が聞こえていた”とは書かれているものの、
彼(作中の殺人犯)が被害妄想に陥った直接的な原因はやはり描写されていなかった。
にも関わらず、多くの批判者が「統合失調症を想起させる」と感じたのはなぜだろうか?
作中の描写から読み解ける範囲では、例えば彼が麻薬中毒者であったとか、
大学内に飾られている絵画に憑りついた幽霊に唆されて凶行に走ったとかであっても、全く矛盾がないはずだ。
しかしながら、批判者は一様に「彼は統合失調症であり、それが凶行の原因として描写されている」と認定している。
(中略)
批判者は、本作が「統合失調症に対する誤った認識・偏見を助長しうる」ことを懸念しているが、
私から見ると、そのような批判者の言動(その外見だけで統合失調症と断定し、凶行の原因と結びつけること)こそが、
統合失調症をとりまく偏見と同質の、謂れなき批判ではないかと思う。

「ステレオタイプ」という問題。
このように批判と擁護の両方の意見を見てきたわけだが、あなたはどう思われるだろうか? あまりにもひどすぎる差別描写だと思うか、それともただのばかばかしい難癖に過ぎないと感じるか。いずれにも理があるように思えるのだが……。
で、ここからはこれらの意見を踏まえ、ぼく自身の私見を述べていく。結論から書くと、ぼくはこの一件を「差別」という名目で告発することは不適当だと考える。
ただ、まったく問題がないとも思わない。やはり作中の描写が偏見を助長する一面はあるのではないだろうか。
どういうことか、くわしく説明していこう。まず、重要なのは「作中にはっきりと犯人が統合失調症患者であることを示す描写はない」という点をどう考えるかという点である。
ぼくはこの事実を認めるが、だからといって即座に「それなら関係ない。問題ないね」とはならないと思う。
わかりやすく、この「統合失調症患者」がもし「オタク」だったらと考えてみよう。
ある作品に、チェックのシャツにバンダナといった「典型的なオタクファッション」を着た人物が出て来て、「ほむらたん萌え~」などと叫びながら女性をレイプする描写があったとする(「さやかたん」でも良い)。
この場合、作中に「この人物はオタクですよ」と記されていなければ、オタクへの侮辱だとか差別だということにはならないといえるだろうか。
もちろんいえないだろう。作中にはっきりとそう書かれていなくても「あきらかにオタクを連想させる描写を行っている」のだったら、それは差別的な描写だといえる。これがつまり「ステレオタイプ」の問題だ。
『ルックバック』は「ステレオタイプ」か?
何らかの属性の人間を明確に連想させたうえでその属性を侮辱する描写をしたなら、たとえ作中にはっきりそうだと明記されていなくても、やはり問題はある。場合によっては、差別として指弾されることになるだろう。
ただ、今回、問題なのは、『ルックバック』作中の描写が、そのような「ステレオタイプ」にあたるかどうかである。
上記の引用部分にも記されていることだが、この場合、作中の殺人犯が統合失調症患者であると考えられる理由は、主にふたつある。ひとつは作品内の理由で、もうひとつは作品外の理由である。
・犯行時、幻聴が聴こえているらしいこと(統合失調症の症状のひとつとして幻聴がある)。
・事件のモデルとも考えられる「京アニ事件」の犯人・青葉真司が統合失調症をわずらっていたと報道されていること。
この両者が絡み合っていわば状況証拠的に「犯人は統合失調症患者である」と考えられているわけだ。なるほど、ひとつだけなら弱いかもしれないが、ふたつそろうと、一定の説得力があるようにも思える。
ただし、幻聴が聴こえる症状が出る病気や障害は統合失調症だけではなく、作家が「京アニ事件」をモデルにしたとする確証もない(そして、仮にそうだとしても、だから作中の犯人が統合失調症だということにはならない)。
おそらく、この点についてはどれほど議論したところで水掛け論にしかならないだろう。結局のところ、「どちらとも受け取れる」というしかないからだ。状況証拠的には「黒」、しかし歴然とした証拠は存在しないのである。
ステレオタイプはバイアスを強化する。
客観的な事実として、じっさいには精神障碍者による犯罪は少ない。統合失調症患者による犯罪はなおさら少数だ。しかし、皆無ではないこともたしかである。
「統合失調症患者は絶対に犯罪を起こしたりしない無垢な存在である」とはいえないのだ。
そうであるなら、作中の犯罪者を統合失調症患者として描いても良いのではないかという意見もあるだろう。じっさいにありえることなのだから。
ただ、この場合、むずかしいのは、作中の描写が世間の偏見を追認する側面があることである。
少し思考実験をしてみよう。ある作品のなかで「右利きの男性」が殺人を犯す描写があったとする。これは「右利きの男性は暴力的で犯罪を犯しやすい」という印象を与える「ステレオタイプ」だといえるだろうか。
ぼくはいえないと思う。なぜなら、読者はその男性ひとりが殺人犯であっても、「右利きの男性」すべてが殺人犯ではないことを即座に了解するだろうから。
このように、たとえ「ステレオタイプ」な描写であっても実際の問題がないことはありえる。
だが、これは『ルックバック』にはあてはまらない。なぜなら、『ルックバック』の場合は、社会的に「統合失調症患者は罪を犯しやすい」というバイアスがあるところに、その種の「ステレオタイプ」が描かれたことこそが問題なのだと考えられているからだ。
あるステレオタイプそのものというより、社会的なバイアスとそれをなぞるステレオタイプの両者がそろうことが問題なのである。
「定番の描写」という安直さ。
つまり、たとえ作中にある「ステレオタイプ」な描写があったとしても、その前に「社会的な偏見の土壌」がなければ問題にはならないということだ。
「ステレオタイプ」の問題とは、すでに社会的に存在しているバイアスを強化してしまうところにあるのである。ただ、繰り返すが、今回の『ルックバック』の描写をそのような「ステレオタイプ」と見るべきかどうかは微妙なところではある。
もっとも、ひとつ客観的な事実としていえるのは、犯人が幻聴を聴いている描写があるということである。ぼくにはこの描写はやはり安易であるようにも思える。
これは「幻聴」と「殺人」を一直線に結ぶ、あまりにもありふれた描写だからだ。その原因が何であれ、マンガのなかに「幻聴」が登場するとき、それはかならずといって良いほど「殺人」を含む「犯罪」と結びつけられていないだろうか?
だが、現実には幻聴から殺人を犯すことなどめったにないことなのである。これは『ルックバック』一作の問題というより、日本のマンガで定番化した描写そのものに安易さがひそんでいるということなのではないかと思う。
ぼくたちは「幻聴が聴こえる」ことと、「人に暴力を振るったり、人を殺したりする」ことをあたりまえのように結びつけた描写に慣れてしまっている。
それはじっさい、よく見かける「いつものこと」である。しかし、それが「いつものこと」になっているのは、やはり「あたりまえのこと」ではないのではないだろうか?
人は偏見から自由になれない。
このような描写が「いつものこと」になっていると、「幻聴」は即座に「犯罪」につながるという印象が刷り込まれる。その可能性は否めない。
たとえば、このマンガを読んだ翌日、あなたの家のとなりに幻聴当事者が引っ越してきたとする(その理由は薬物中毒かもしれないしアルコール依存症かもしれないし統合失調症かもしれない。何でもいい)。
あなたは作中の描写を思い出し、いくらか怖くなったりしないだろうか? 現実には幻聴が聴こえるからといってすぐに殺人を犯すわけではないし、おそらくはあなたも理性ではそのことをわかっている。
それでも、やはり不気味な印象は否めないのでは? もしそうなのだとしたら、それはあなたの心に新たな偏見が刻み込まれたということである。
その意味で、『ルックバック』の描写はいくらか安易であったかもしれない。これほど細部まで考え抜かれた天才的なマンガであるにもかかわらず、その部分の描写が定番のものに留まっていることに注目するべきだろう。
そこにはどのような理由があるのだろうか。いずれにせよ、画竜点睛を欠く印象ではある。ぼくはそれを「差別」だとは思わないが、あくまでエンターテインメントの技法的なクオリティの問題として、もっとほかの描写があったのではないか、とは思ってしまう。もちろん、単なるアマチュアの一読者の感想に過ぎないわけだが……。
この作品に対するぼくの意見はこのくらいである。
お薬を飲んで寝ますね。
最後に、今回の件について検索している最中に見かけた「ガチ差別」ツイートの数々を引用しておこう。『ルックバック』と違って、これらのツイートに同情の余地はない。ぼくはこれらの発言を心から軽蔑するものである。
「薬を飲んで寝ろ」? そうすることにするよ。病気は薬で治るけれど、ここまで歪んだ人格は治しようがないからな! それでは、皆さん、おやすみなさい。